


Photo by (c)Tomoyuki.U(http://www.yunphoto.net)
翌日の月曜日、バイトを終えていつものように7500円もらった後、家に寄って昨日受け取った袋をメット入れの中にしまって、高松君の家へと向かった。
「――というわけで、記事を書かせてもらえることになってさ。なんか、え、まじで? って感じ。でさ、ゲームカセットとか設定資料とかもらってきてさ、ほら見てよ、基盤剥き出しのカセットなんだよ。なんか業界って感じしない?」
高松君の部屋に上がり、袋の中身を全部広げて私はまくし立てた。分厚い設定資料集と、何に使うのかよくわからないセル画、雑誌レイアウトの見本、そして基盤剥き出しのゲームカセット。普通に生きていたらまずお目にかかれない代物だ。
「するする」
日頃冷静沈着な高松君も興奮していた。
ゲームライター募集の広告を見て編集部に乗り込んだ人間というのは、同級生では私が最初だっただろう。多分、今でも私だけだと思う。友達の友達でそういうのがいたという話も聞かない。まったく未知の世界、どちらかという日常から懸け離れた所だと思っていた世界に勢いだけで乗り込んでいって仕事を得てしまったのだから10代の二人が興奮するのも無理はなかった。
「なんかさ、え、内藤九段将棋秘伝の紹介文だけでいいの? って感じ。だって、400字ぐらいだよ。それで雑誌の記事書かせるなんて、びっくりだよ」
「そうだよなぁ、いや、俺もさ、工藤から編集部に行くって聞いた時はそんなに甘くないだろと正直思っていたから、まさか基盤剥き出しのゲームカセット持ってくるとは思わなかったよ」
私と高松君は、しばらくの間、ライターというのは案外数が少なくて、売り手市場なのではないかという話をした。なりたい人はたくさんいるが、編集長の従兄の子供とか、その業界に以前いた人とか、“選ばれた人たち”がやっているものだとばかり思っていた。ところが、19歳の高卒がコネもないのに単身乗り込んで、ライターデビューを決めてしまったのである。
「ひょっとすると、文章を書く仕事っていうのは行動力さえあればなんとかなっちゃうのかもしれないな。美人でさ、彼氏がいると思われて彼氏が出来ないっていう人いるじゃん。そういう風な感じで、ライターも憧れる人は多いけど、なる人は決まっていると思って、みんな敬遠してるんじゃないか」
「案外そんなもんかもしれないね」
二人はわかったような顔をして頷き合った。
まさか数年後、アルバイト生活から脱して、これからは文章一本で飯を食おうと決心し、バイトを辞め、就職情報誌を見て編集プロダクションやライターの求人に片っ端から応募したら、
「今回はご縁がなかったということで――」
「残念ながらご希望に添えない結果と――」
「末筆ながら今後のご活躍をお祈り申――」
「遺憾ながら今回は採用を見送らせて――」
「大変残念ですが不採用ということに――」
という手紙と共に履歴書が全部返ってくるという悲惨な事態に陥るとは想像すら出来なかった。
「とりあえずさ、雑誌をもう一度見てみようよ。なんか、ページのレイアウトみたいのもやらないといけないらしいんだ」
「へえ」
私と高松君は向かい合って共にあぐらをかきながら、真ん中に見本としてもらってきた数冊のゲームボーイ誌を広げ、覗くように見た。
「まず、大作の特集があって、スーファミ、ファミコンなんかの普通の新作の紹介が来て、ちょっと攻略が入って、読者ページ、で、膨大な広告と」
「この広告が凄いよね。ゲームのコピー機の広告とか出ちゃってるもんな」
「『AVポーカー 木田彩水/鮎川真理/藤木流花』とか、ハッカー(という、ファミコンでアダルトゲームだけを出していたインディーズメーカーがあった)のゲームの買い取り広告が出ているのってこの雑誌だけだろうな、多分」
「この、小説はなんなんだろうね」
高松君がページをめくっていた手を止めて言った。
タイトル、作者の名前などはすっかり忘れてしまったが、妙にページ数の多い連載小説が掲載されていた。内容もかなり不確かな記憶しかないのだが、世間知らずのお嬢様と勇者なんだか泥棒なんだかが冒険の旅に出るとか、そんな感じのファンタジーだった。読者に人気があるのか、投稿イラストのページまであった。
「ドキドキのわくわくですわ、だって」
高松君がぽつりと言った。
ヒロインの口癖らしく、彼女を描いたイラストの横には全部その台詞が書いてある。他にも、「失敗した」とか「うわ~なんか変」とか自身のイラストの出来に対する言い訳のような言葉が細かい字で書いてある。
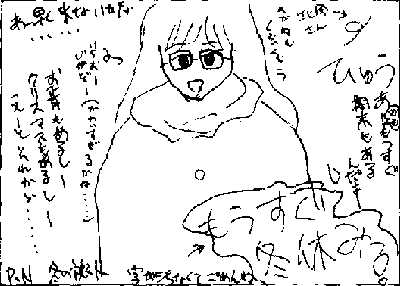
参考資料1
エッセイ&日記で使った、『昔よく見かけた投稿はがき』の例
「やっぱ、こういうノリの小説っていうのはゲームをやる人間には人気あるのかな。これぐらいだったら俺の小説を載せてもらってもいいと思うんだけどな」
私は顎の無精髭を右手の中指でさすりながら言った。
ゲームボーイ誌の連載小説の作者も、
「やあ、あなたが竹内探偵ですね? うわさは、きいております。となりにいるのは工藤社長じゃないですか」とろう人は、あかるい声でいった。
「私の名前をおもえててくれてこうえいです」と工藤は頭をペコリとさげた。
こんな小説を書いていた人間に言われたくはなかっただろう。
しばらく小説の話をした後、読者欄を見て、高松君が言った。
「とりあえず一通り見たけど、ページのデザインは単純だよね」
私たちがファミマガやファミコン通信で見ていたページデザインというのは、大小変化に富んだ見出し、バランスよくちりばめられた画面写真、右下辺りに開発者のコメントと読者に飽きさせない、刺激を与える作りだったが、ゲームボーイ誌のページデザインは、見出しが右にあって本文、一番左に画面写真というのが四段ぐらい重なっているだけという至極単純なものだった。
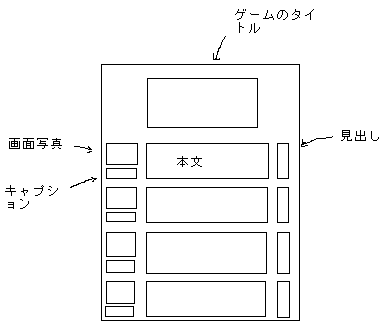
参考資料2
ゲームボーイ誌のページレイアウト
「そうだよなぁ。こういうレイアウトとかよくわかんないけど、やっぱり、ライターにやらせているからこんなに単純なのかな。っていうか、そもそもライターがやるもんなんだろうか」
「俺もよくわかんないけど、普通はライターはやらないんじゃないか?」
二人は共に首を傾げて、改めてゲーム紹介ページを見た。
「文章のノリはファミコン通信とかとあんまり変わらないよね。やってみるぞ、とか、攻略するぜ、とか」
「勢いはある、みたいな」
「そうそう」
私は腕を組んでしばらく考えた後、こう切り出した。
「じゃあさ、二人で分業でやってみよう。俺が文章を担当するからさ、レイアウトやってよ。それで、原稿料は折半ということにしない?」
私がそう言ったのは、デザインセンスがゼロだったということもあるが、この記念すべき初めての文章の仕事を、唯一の理解者である高松君と共にやりたいということが大きかった。最初の一歩を彼と共に踏んでみたいと思ったのだ。
「え、別にいいけど」
高松君はちょっと戸惑っていて、デザインはやってもいいけど原稿料はいらないと言ったが、私が無理矢理説得して最終的に承諾した。
家に帰って、基盤剥き出しのカセットに差し込み、1時間ほどプレイしてみた。
ロボットみたいなキャラクターによる1対1のドッジボールというのが基本で、そこにハンドボールの要素がかぶってくる。画面効果はわりと派手でずっと見ていると目に悪そうだ。幸いにしてどうしようもなくつまらないクソゲーではなく、そこそこ遊べるゲームだった。
レイアウトが決まってから、編集部が文字数の連絡をしてきて、それから書き始めるというのが基本だったが、試しにフリーで書いてみた。
究極のオリジナル闘球が、今、敢然と我々の目の前に姿を現した! 芸術とも言える格闘ロマンを体験出来るスーパーソフト「プラズマ・ボール」。左右親指の神経を、一気にオーバーヒートさせる過激なACTゲームだ。
舞台となるのは、遥か時空の彼方にある地球とよく似た惑星「エレメント」。この惑星では1000年に1度、《風・木・火・水・金属・土》の6人の神々が天空にある「神界」に集まり壮大な激闘球技「プラズマ・ボール」を行う。いつも温厚な神が「闘神」へと姿を変え、超エネルギーボールを使い時空を超えた闘いを繰り広げるのだ。(実際に雑誌に掲載された文章です)
「まあ、こんな感じかな」
常日頃、
ついに天才・工藤圭が動き出した。単なる内輪受け小説とは桁が違う。
作者自身、「江戸川乱歩賞を軽く取れるような作品に仕上がった」というだけあって、この作品のクオリティは最高に高い。まさに永遠に人々に語り継がれる作品の誕生だ。なお、原作者の工藤圭自身がお茶汲みを担当していることでも注目を集めている。
工藤 圭 ●プロフィール
平成元年に**専門学校**コースを、入学してから3日で中退。本格的に、小説家としての道を歩き出した。現在、地元の皇帝を務めている。血液型B型。主な作品に「道化師の聖戦」がある。
自分の小説を友達に読ませる前にこんな宣伝チラシを配って、母親に「一度診てもらった方がいい」と言われる経験が活きたのか、思いの外うまく書くことが出来た。
数日後、高松君から「レイアウトが出来たんだけど」という連絡をもらい、彼の家まで受け取りに行った。
「こんな感じなんだけど」
白い紙に鉛筆で書かれたレイアウトは、同一フォーマット四段重ねの、いわゆるゲームボーイ誌標準レイアウトだった。
「まあ、こういう風になるよなぁ」
見本として渡されたゲームボーイ誌にはこのレイアウトしかないのだから、他に書きようがない。思いっきり崩して文句を言われるぐらいなら、標準をそのまま採用した方がいいだろう。
私はお礼を言って受け取り、早速、コンビニのFAXから編集部へと送信した。
翌日の夜。
トゥルルルルル――
電話が鳴った。
次回、『初めての挑戦 4』につづく