


Photo by (c)Tomoyuki.U(http://www.yunphoto.net)
すべて自分で出来るというのは本当に魅力的だった。なにしろ、小学生の時、「俺はヒヤシンスの球根の状態より、マンモスとUFOについて書きたい」と言ったが、誰も賛同してくれなかったので班を離れて独りで壁新聞(ちなみに名前は工藤新聞)を書いた人間である。授業参観に訪れた親たちは、教室の後ろの壁に貼られている壁新聞を一つ一つ見ていく中で、
![]()
![]()

![]()
![]()
「わたしたちが子供の頃もヒヤシンスの水栽培したわねぇ」
「そうね。懐かしい」
「でも、たまに咲かないのがあるのよね」
「そうそう、あれなんでかしら。おほほ」
![]()
![]()
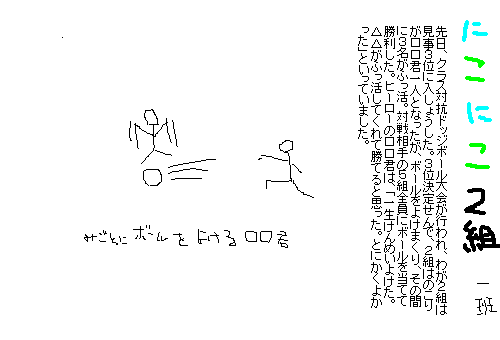
![]()
![]()
「うちの子は暇さえあれば、ドッジボールとあげパンの話してるわ」
「ほんと、子供ってドッジボール好きよねぇ」
「でも、まあいいじゃない。やっぱり男の子は運動しているのが一番」
「そうね。何時間もゲームやっている姿を見ていると頭にきちゃうわ。おほほ」
![]()
![]()
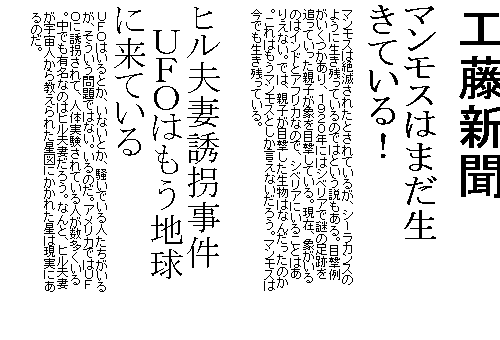
![]()
![]()
「……」
「……」
と、学級新聞というより恐怖新聞を連想させる私の壁新聞を目の当たりにして(なんでこの新聞だけ個人名が付いているのかしら……)と疑問に思いつつ、クラスとまったく関係がなく、しかも裏の取れていない情報をなんの疑いもなく事実と断定している文章を読んで絶句したことだろう。
話が脱線したので元に戻そう。
今請け負っている仕事が全部終わらないと出来ないですけど、本当にそれでいいですか? と念を押して、それで構わないという返事をもらったので、この依頼も受けることにした。
本当にわずかな時間で、私は、小説の執筆2つと合わせて、連載になるかもしれないショートミステリの執筆、18禁ゲームのシナリオ執筆、ビジネス書の執筆、ゲーム副読本の執筆と向こう2年ぐらいの仕事を請け負うことになった。
いわゆる“フリーター”だった私にとって、先の仕事が決まっているというのは妙な感じだった。短期のバイトならだいたい一カ月先、長期は淡々と日々与えられた仕事をこなしていくという感じで、来年のプロジェクトは、とか、半年後のイベントの企画は、なんていう話にはまったく縁がないし、入れない。一年後に自分がどうなっているのか断言出来るフリーターは一人もいないと言っても過言ではないだろう。たとえ一年間契約していたとしても、明日の朝、自転車がパンクして15分遅刻したら解雇される可能性だってあるのだ。
そしてもう一つ、名指しで仕事を依頼されるのも不思議な気がした。派遣でバイトに行っていた時、「社員には何を言われても、たとえ間違ったことを言われたとしても反論するな。あなた方は言い返せるような立場にはいない。もし社員からクレームが来たら首を切ることになる」と言われた。それがバイトだと言われればそれまでで、私はすっかりそういう関係に慣れてしまっていた。だから、雇う側がメールや手紙を書いて是非にと頭を下げて頼んでくるなんて、変な気分だった。
「ふう」
そうため息をついて、居間で昼食を取ろうと立ち上がると電話が鳴った。仕事の話かなと思い、痛み始めた胃の辺りを抑えて受話器を取ると、聞き慣れた、それでいて懐かしい声が聞こえてきた。
「もしもし圭くん?」
「……」
ちょっと甲高い、本人曰く“アニメ声”が耳元で響く。
呆気に取られて声が出なかった。毎日毎日、寂しい、早く会いたいと書かれたエアメールが届いて、私も同じように思っていたのに、いざ声を聞くと何も言えなくなってしまった。
「もしもーし」
彼女はそう言った後、わざと言葉を区切りながら続けた。
「た、だ、い、ま」
受話器から、くすくすと笑う声が聞こえてくる。私が無言なのがおかしいらしい。私は事態を把握するためになぜか恐る恐る尋ねた。
「……アメリカから?」
私の言葉に彼女は声を上げて笑った。
「どうして」
彼女が口元を綻ばせている姿が想像できる。
「ただいまって言ったでしょ。もう日本にいるよ」
彼女――彩実ちゃんはそう言った。