小説家になりたいという人が、ほぼ必ずぶつかる壁の一つに『頭の中に大傑作として存在しているストーリーを実際に書くと、どういうわけかつまらなくなる問題』というのがある。これは、『頭の中に大傑作として存在しているストーリーを友達に話すと反応が妙に薄く、やる気を失う問題』と根は同じである。
小説家志望にとってこの問題がやっかいなのは、こじらせると、
- 文字にするとつまらなくなるので書かなくなる(現実逃避)
- プロの小説家を尊敬できない(自分の頭の中のイメージ>プロの小説 だから)
- 尊敬できないプロが世間では自分より認められるので、つい俺の方が凄いと言ってしまうが、書いていないので認められない(孤立化)
- 自分の世界に籠もる(更なる現実逃避)
- 尊敬できない作家がもてはやされている世の中は間違っていると思うので、クーデターや世界の滅亡を願う(チャラになれば、今度は自分が注目されるのではという願望)
- そんなことを願っているうちに、どうにもならない年齢になる
といった感じで、いわゆる“負のスパイラル”に陥りやすいことだ。私もこのスパイラルにはまったことのある一人だ。
このスパイラルから脱出する方法はいくつかあると思うが、手っ取り早いのは、頭の中の大傑作を文字にするとつまらなくなるのはなぜなのかを知ることだと思う。
どうすればわかりやすくなるかいろいろと考えてみたが、麻雀でたとえてみたい。
まず、世間一般で言われる『傑作』を役満の手だとする。
役満の例
緑一色(リューイーソー)
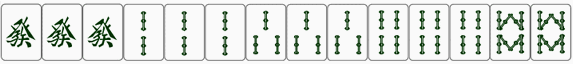
緑のみで図柄が刻まれている牌だけで構成される
素材:フリー素材の来夢来人
麻雀というのは基本的に、四人に13枚ずつ牌が配られ、配られた以外の牌を一人ずつ引いていって、役を作るというゲームである。牌は数種類あり、それぞれ数字や絵が書かれていて、種類ごとに同じ数字を揃えたり、同じ種類で数字を順番に並べると役がつく。
配られた時点で役になっているという場合もあるが、普通は何度も牌を引いたり、相手から牌を取ったりして役を作っていく。つまり、役満の手というのは最初から用意されているものではなく、偶然とか駆け引きとかいろいろなものが結びついて形になったものである。
小説も似たようなもので、作家の頭の中に小説の材料がごちゃごちゃと揃った時点で傑作が約束されるということはまずあり得ない。作家の経験や思考、能力、時代の流れ、運、編集者、出版社、宣伝など、いろいろなものが絡まり合い、傑作(と呼ばれる物)が出来上がる。
では、小説家志望の頭の中にある大傑作イメージは麻雀で言うとなんなのかというと、実戦ではなく一人で牌を揃えて役満の手を並べた瞬間を切り取ったものなんだと思う。たとえば、リューイーソーなら、既にリーチになっていて、表になって見えている發を加えた前後のイメージという感じだ。堂々たるクライマックスシーンを思い描いて恍惚となってしまう。どういう経緯でそうなったかというものは点のようなものだけ。
友達に伝える場合は、
「見て見て、俺、リューイーソー揃えちゃった、すごくね?」
といった感じだろうか。
しかし、リューイーソーを含めた役満の手が評価されるのは、実戦で揃えたということに対してであって、リューイーソーの牌の並び自体がすごいわけではない。自由に牌を取ってリューイーソーの形に並べて、それを大勢に見てもらっても誰もなんとも思わないだろう。友達に、自分が考えた傑作と信じて疑わない大まかなストーリーとクライマックスシーンを興奮気味に話しても、大抵、薄い反応しか返ってこないのはそのためだ。
ただ、イメージを口にしている小説家志望本人が、別の小説家志望から同じようにイメージだけを熱く語られたら、そんなこと言われても、通して読んでみないとわからないよねと思うはずである。なぜ、他人から聞くとおかしさがわかるのに、自分で言う場合はわからないのか。おそらく、作者としての補正が効いてしまうからだろう。
頭の中の大傑作を文字にするとつまらなくなるのも、麻雀で考えればわかりやすい。いくら、役満の手をイメージして進めていっても、そもそも配牌が狙っている手にまったく合わなかったり(キャラクター設定の失敗)、捨てる牌を間違えれば(構成の失敗)役満の手の出来損ないのようなノーテンの手が出来るだけだろう。配牌を無視して特定の役のみ狙えば上がれる確率は低くなる。
また、イメージに自信がある小説家志望の人は、しばしば、プロの作家の作品に対して「俺だったらもっとうまく書ける」と口にする。大抵の場合、麻雀で言うとツモと打牌をだいぶ繰り返して、ある程度、牌が整った状況から引き継げば、である。その形まで持っていくという作業が抜けている。小説で言うと、中盤までのストーリーと、キャラクターの設定を引き継げばもっと面白く書けると言っているようなもので、そこを軽く考えて自分で一から書くと、当然、苦労することになる。
リューイーソーに比べれば、簡単に作れるイーペーコーや平和はちょっとかっこ悪い。まだ小説を書いたことはないという小説家志望からすれば、そういった地味な役を感じさせる小説を書いている作家は尊敬の対象にはならないかもしれない。しかし、実戦では、役満を狙ってテンパイにいくつも足りないようなノーテンよりは、イーペーコーで上がった方がはるかに評価される。どんなに配牌や流れが悪くても、駆け引きと知恵でなんとかテンパイまで持っていったり、役を作って上がる、その姿もまたプロだからだ。
役満の手を作れないなら麻雀をやらないというのでは未来がない。まずは実戦を行う、テンパイまでは持っていく、安い手でもいいから上がる、そういったことを繰り返しているうちに、ある日ふと、役満を狙える配牌が来るのだと思う。
というわけで、役満の手を作れないなら書かないと決めて、そのうちなにも書けなくなってしまったという人に対しては、まずは実戦で打ち切ってみるってだけでいいじゃんと言いたい。
デビュー作である『わたしの彼はハムスター!?』を書いたとき、誉めてくれる人はごくわずか、それも私のことを知っているから誉めてくれているんだろうなという感じだった。あとは箸にも棒にもかからない、ボロクソ、糞味噌、失笑、苦笑、そんな言葉で表せる感想が多かった。
近くにいた人からすれば、「俺は役満で上がると常々豪語していた人間が、いざ書いたらこれ?」的なものもあっただろう。
でも、本は出版された。書ききって自信になった。国会図書館に納入された。中学生の女の子からファンレターをもらった。客観的に見れば、テンパイになっているかどうかも怪しいという出来なのかもしれないが、実戦に打って出て、一応、歴史に名を刻んだ。
役満で上がることにこだわっていたら、役満でのみ上がる自分が本当の自分だと思い続けていたら、なにもないまま今日を迎えていただろう。
