第17回 湘南物語 ある高校生の青い文通(6/6)
放送が終わり、電話がかかってきた。中学校の友人からだ。
「テレビ観てたらいきなり出てきてびっくりしたよ」
その後も何本かきて、反響の大きさがわかった。ゴールデンタイム+とんねるずだ。私たちの年代だったらかなりの人間が観ていただろう。
(彼女も観ていたかな)
そしたら悲劇だ。あんな顔を見たら、彼女はどう思うだろうか。いくらもう関係ないとは言え、気になる。
それからしばらくの間は、学校でも地元でもその話題で持ちきりだったのだが、やがて風化し、季節は春になり、私は高校2年に進学した。
この時点で麗華のことはすっかり忘れていた。彼女が出来る雰囲気はまったくなかったが。
ある日、家にいた私は郵便受けに手紙が入った音を聞き、それを取りに行った。
「ん?」
拾い上げて見てみると、封筒になんだかごちゃごちゃ字が書いてある。
「なんだこれ?」
私はなんだか胸騒ぎを覚えながら、差出人の名前を見た。
綾小路麗華
手紙には確かにそう書かれていた。
(……なぜ、今頃)
私は一人で動揺していた。封筒がやけに薄っぺらいことと、そこにごちゃごちゃ書かれてある文字が気になる。
封筒に書いてある文字と言えば、以前、好きな女の子からもらった手紙(封筒)に英語が書かれていて、「これはきっと、彼女からの俺へのメッセージなんだ。わざと英語で書いて俺の教養を試しているんだ!」と考え、辞書片手に和訳していたところ、しばらくしてからその英語は、封筒のデザインだと気づいたという情けない話がある。私は当時、ドラゴンクエスト2のやりすぎで、視力をかなり落としていたので、細かい字はよく見えなかったのだ。印刷と手書きの判断もつかなかったぐらいに。
私は目を細めて、ごちゃごちゃ書かれてある字を見た。よく見ると、いろんな筆跡があり、複数の人間によって書かれたものだということがわかった。
そして衝撃的な一文が飛び込んできた。
-テレビ映りさいてー!!-
がーん!!
それだけじゃない。
「げろげろー」
「中山美穂と抱き合ってうれしかった?」
「さいてー」
などの文章が至るところに書かれてあったのだ。もう半端じゃない。30ぐらいそういう文書が書かれている。恐らく、手紙を出す段階でいろんな人間に封筒を回したのだろう。
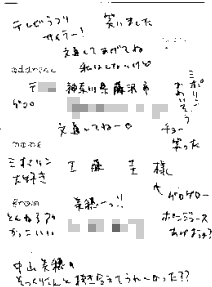
記憶を元に封筒を再現したもの。ひど過ぎる(笑)。
それにしても、手紙に書くならまだしも、普通、封筒に書くだろうか。郵便局の人はさぞかし笑っただろう。
私は頭にかあっと血が上るのを感じた。
「なんなんだ、あの女は!」
ここで強硬手段出なかった当時の俺に拍手したい。今だったら、青春18キップ買って、即刻愛媛に殴り込みだろう。
そのまま手紙を捨てようかとも思ったが、何が書いてあるのか興味があったので、一応開けて見てみた。
工藤君へ
文通中止しちゃってごめんなさい。でも、新しくやりたいという人がいたので、その人の住所と電話番号を書いておきます。絶対に文通してあげて下さい。では、さようなら
手紙にはその人の名前と住所と電話番号が書かれてあった。恐らく、新しくやりたいという女の子は彼女たちのグループから嫌われているような女の子なんだろう。もし私から返事が来たら揃って馬鹿にしようという魂胆だ。
こんな失礼な女がいるのだ、実際。
「すごくはずかしがり屋で、友達としか普通に喋れない」
彼女からの最初の手紙にあった自己紹介を思い出す。そんな内気な女の子が、こんな手紙を平気で送ってくるんだから世の中というのはわからない。
普通だったら「こんな女がいました、終わり」だと思うのだが、話はまだ続いてしまう。
季節は忘れたが、この事件のあった年の、秋ではなかったかと記憶している。
夜の7時頃。
私はサッポロ一番塩ラーメンを食していた。
部屋には羽賀君(仮名)がファミスタをやりに来ていた。彼は自分ではファミコンを持っていなかったのだが、しょっちゅううちにやりに来るので、私が持っているゲームは私同様にうまくなるという、対戦相手としてはもってこいの男だ。
彼のプレイを見ながら、私がラーメンを口に入れた瞬間、電話がかかってきた。
(なんだよ、こんな時に)
私はそんなことを思いながら、電話に出た。どうせ妹の友達だろう。
「もしもし、工藤ですけど」
「……もしもし」
ちょっと暗い感じの、女性の声だった。
「どちら様でしょうか」
「綾小路ですけど」
(なにー!!)
私は自分の耳を疑った。あの究極失礼女が、ぬけぬけと私の家に電話をかけてくるとは!!
いったいなんだと言うのだ。
「え、あの、なに?」
だが、私は完全に動揺していた。あの女に対して、こんな柔らかい物腰でしか対応出来ないというのも情けない。
「私たちね、今度、修学旅行に行くでしょう。だから東京で会えないかなあって」
「え!?」
おいおいちょっと待て。
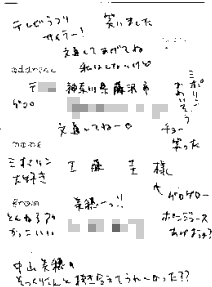
これを出しておいて東京で会えないかなあってってなんだよ。おまえ、東京で男に会うことに憧れてんだろう。それでとりあえず知っている奴に電話したんだろう。ドラマの見過ぎじゃないのか? ――と言えるはずもなく、
「ちょっと佐伯に相談してみないとわかんないなぁ」
と誤魔化した。
とにかく、一度電話を切って頭の中で考えを整理したい。相手の性格は最悪だが、もしかして可愛いかもしれない。ひょっとして会ったらあの手紙にも目を瞑れるかもしれない。だが、会うのはどう考えてもギャンブルだ。
「じゃあ、工藤君はどこで会うのがいいと思う? 私ら東京あんまりしらんけんねぇ」
そう言われても、私もよく知らないので困る。だいたい、いつの間にか話が「会う」という方向で進んでいる。どこまで図々しい女なのだろう。
「代々木公園とかかな」
そう思いながらも会う場所を挙げてしまう辺り、私もかなり情けない男だと言える。
「え、そこどこにあるの?」
「原宿の方にあるんだよ」
わかったような説明をしているが、ただの一回、代々木第一体育館におニャン子クラブのコンサートを見に行った時に通ったから知っている、などとは口が裂けても言えない。
「えー、ぜんぜんわからんよ。説明してくれないと」
「そうだな、ま、いけばわかるよ」
「えーっ」
話は完璧会う方向だ。もうこの流れは止めらない。会いたくもない相手に、なぜ「会いたくない」と言えないのだろうか。やはり根は小心者だからだろうか。
「じゃあ、また電話する。じゃあね、ばいばい」
「うん、じゃあね」
私は電話を切って、すぐに佐伯君の家に掛けた。
「――というわけなんだけど」
「まじかよ」
「どうする?」
「別に行ってもいいけどさ。平日だぜ。学校休まなきゃ」
「そうだよな。やっぱやめとくか」
「そうだな」
佐伯君と簡単に話がまとまり、私は行かないことを完全に決意した。やはりどう考えても、あの手紙を送ってきた女に呼び出されて会うのは馬鹿である。
そして10分後、電話がかかってきた。
「もしもし工藤ですけど」
「あ、綾小路ですけど」
「ああ」
「佐伯君と話した?」
「うん、話したよ」
「なんだって?」
「あのさ、もし俺たちが行かない場合は、どうなるんだろう?」
「その時は私たちは終わりよ」
終わる前に始まっていないと思うし、仮に始まっていたとしてもとっくの昔に終わっていると思うのだが、彼女はそう言い切った。内気というわりには言うことが大胆だ。
「終わりだって……」
彼女の後ろに女の子が数人いるのがわかる。くすくすと笑い声がするのだ。彼女としては東京で男を呼び出すというのは、自分の地位を高めるためにも必要なことなのだろう。
「あのさ、行かないことにしたよ。学校休めないしね」
「……」
「それじゃあ」
「ああ、そう」
彼女はいつもの暗い声に戻ってそう言った。
「さようなら」
「……」
電話は無言のまま切れた。
ようやく終わったという安堵感と、ぬけぬけと電話してきた彼女を簡単に受け入れてしまったという情けない気持ちが交差していた。
しかし、終わったのだ。もう、これでいい。
「じゃあ、ゲームやるか」
私はファミコンのコントローラーを手に取った。
それから彼女から電話がかかってくることはなかった。
「今頃、どうしているんだろう」
最近、ふと、そんなことを思うときがある。しかし、街で偶然会ったとしても、気づくことはないだろう。でも、その時、お互い目が合ったら相手のことをどう思うのだろうか。ちょっとだけ気になる。
-完-
